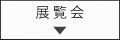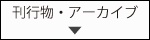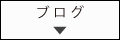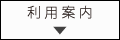江戸時代、日本で唯一外国に門戸を開いていた港町長崎には中国・オランダなどからさまざまな“もの”が入ってきた。その中には、書籍・絵画なども多く、またあわせて中国より文人画家も来舶し、彼らのもとで長崎の画人たちが画を学び、その指導のもと多くの文人画家たちが育っている。文人画は文字通り、中国において専門画家ではない、学者・医者・官吏などの文人が描いた絵であり、わが国の文人画家たちの経歴もまた、武士・儒者・医者・商家など多種にわたっている。
鎖国体制下にあって、長崎という特殊な環境で生まれた職業に乙名職がある。「おとな」と読む長崎奉行に属する町役人のことで、町の支配を任され、市政をはじめ出島管理などを行った。この乙名職を代々勤める家に生まれ、自らもこの職を勤めた経歴をもつ木下逸雲(きのした いつうん)は、後に長崎を代表する文人画家となる。
江戸時代、日本で唯一外国に門戸を開いていた港町長崎には中国・オランダなどからさまざまな“もの”が入ってきた。その中には、書籍・絵画なども多く、またあわせて中国より文人画家も来舶し、彼らのもとで長崎の画人たちが画を学び、その指導のもと多くの文人画家たちが育っている。文人画は文字通り、中国において専門画家ではない、学者・医者・官吏などの文人が描いた絵であり、わが国の文人画家たちの経歴もまた、武士・儒者・医者・商家など多種にわたっている。
鎖国体制下にあって、長崎という特殊な環境で生まれた職業に乙名職がある。「おとな」と読む長崎奉行に属する町役人のことで、町の支配を任され、市政をはじめ出島管理などを行った。この乙名職を代々勤める家に生まれ、自らもこの職を勤めた経歴をもつ木下逸雲(きのした いつうん)は、後に長崎を代表する文人画家となる。
逸雲は、寛政11年(1799)、木下清左衛門勝茂の四男として、長崎八幡町(長崎市)で生まれた。木下家は本姓藤原氏で、代々八幡町の乙名を勤める家柄で、逸雲も兄の隠居後、18歳でその役を継ぐが、若年より医学の勉強をしたいという志しがあり、職を兄の子に譲り、本格的に医学の勉強を始め、内科・外科の二科を兼ねた医師となり、医門名を得生堂と称した。
ところで、逸雲は多芸多才な人で、絵画はもとより、書・篆刻を能くし、琵琶の演奏・制作に巧みで、煎茶をたしなみ、藤原相宰の名で和歌を詠むなど、それぞれに一家をなすほど精通するが、その中でも特に画家として著名である。絵は、初め地元の石崎融思(いしざき ゆうし:1768~1846)に学ぶ。石崎家は「唐絵目利(からえめきき)」四家のうちの一つで、この唐絵目利というのも、 長崎にしかない職業で江戸時代中期に長崎奉行所内に設けられた。中国から船載されてきた書画や器物の鑑定と価値の評価、さらに輸出入の交易品や鳥獣類などの写図の作成が主な職務であった。また長崎奉行所の御用絵師を兼務することが多かった。融思の元で学んだ後、逸雲はさらに雪舟、狩野派、大和絵、円山四条派などの諸流派の研究にも専心し、水墨、淡彩、著色の技法を駆使して、細密画から大津絵に至るまで実に様々な絵を描いた。西洋画法にも関心を持ち、西洋絵の具の研究も熱心に行った。また、白磁染付で知られる亀山焼の発展に尽くし、自ら絵付けも行っているが、文人画風の雅味のある焼物と評判となった。
長崎にしかない職業で江戸時代中期に長崎奉行所内に設けられた。中国から船載されてきた書画や器物の鑑定と価値の評価、さらに輸出入の交易品や鳥獣類などの写図の作成が主な職務であった。また長崎奉行所の御用絵師を兼務することが多かった。融思の元で学んだ後、逸雲はさらに雪舟、狩野派、大和絵、円山四条派などの諸流派の研究にも専心し、水墨、淡彩、著色の技法を駆使して、細密画から大津絵に至るまで実に様々な絵を描いた。西洋画法にも関心を持ち、西洋絵の具の研究も熱心に行った。また、白磁染付で知られる亀山焼の発展に尽くし、自ら絵付けも行っているが、文人画風の雅味のある焼物と評判となった。
長崎画壇興隆の基礎を築いた逸雲の自信はたいしたもので、慶応2年(1866)4月、諸国の名勝を探ろうと京阪・江戸に漫遊した際、江戸から長崎の門人に送った書簡には「長崎の南画、当時日本第一、他に見るべきものなし」と書いている。


近江の文化財