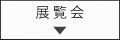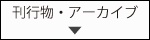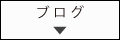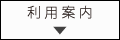桑山玉洲(くわやま ぎょくしゅう)は、江戸時代中期の文人画家であり、美術評論家としても知られた。玉洲は、延享3年(1746)に紀州和歌浦で廻船業と両替商を営む桑山昌澄の子として生まれ家業を継いでからも、新たに新田開発事業を興すなど、経済的環境に恵まれ、青年期を事業家として過ごすかたわら、画業にも傾倒していった。
桑山玉洲(くわやま ぎょくしゅう)は、江戸時代中期の文人画家であり、美術評論家としても知られた。玉洲は、延享3年(1746)に紀州和歌浦で廻船業と両替商を営む桑山昌澄の子として生まれ家業を継いでからも、新たに新田開発事業を興すなど、経済的環境に恵まれ、青年期を事業家として過ごすかたわら、画業にも傾倒していった。
玉洲が45歳のときに著した『玉洲画趣(がしゅ)』で次のように振り返っている。「もともと愚かな私である上に、辺鄙(へんぴ)なところに住んでいたので、画の先生や友人は一切おりませんでした。ただ、幼少のときから古書画を評論することが好きで、明和安永の頃に数度江戸へ行き、当時の有名な画家たちを尋ねてみましたが、自分に合うものがなく、その門に入ることもしませんでした。」といい、裕福な商家という好条件のもと、江戸の諸名家を訪ね、画や画論を研究して自己形成したとし、まったくの独学独習であることを主張している。 さらに、「その後しばらくして、京都や大坂を訪れたとき、池大雅や木村蒹葭堂らと交流することによって、書画を評論することを悟ったのです。したがって、画の先生というものはいませんでした。ただ幼年より自分独自の画を描いて成就したいと思い、一枚も他人の画を模倣したことはございません。」と続ける。玉洲30歳代の頃と思われ、この頃京阪に遊学して、大雅や蒹葭堂らとの親交を通じて、彼らの感化を受けながら画家として一つの方向性を見出していく。それは文人としての理想郷を描いた山水画というジャンルである。玉洲は山水表現において、のびやかな線と明るい色彩による独自の画風を確立していくが、一つの型におさまるのではなく、絶えず創意を盛り込もうとしていることが画面からうかがわれる。
さらに、「その後しばらくして、京都や大坂を訪れたとき、池大雅や木村蒹葭堂らと交流することによって、書画を評論することを悟ったのです。したがって、画の先生というものはいませんでした。ただ幼年より自分独自の画を描いて成就したいと思い、一枚も他人の画を模倣したことはございません。」と続ける。玉洲30歳代の頃と思われ、この頃京阪に遊学して、大雅や蒹葭堂らとの親交を通じて、彼らの感化を受けながら画家として一つの方向性を見出していく。それは文人としての理想郷を描いた山水画というジャンルである。玉洲は山水表現において、のびやかな線と明るい色彩による独自の画風を確立していくが、一つの型におさまるのではなく、絶えず創意を盛り込もうとしていることが画面からうかがわれる。
玉洲は生前、あまり脚光を浴びた画家ではなかった。しかしそれは必ずしも画家として不遇であったわけではなく、別に職業を持ちながら、その傍らで画筆を執るという、いわゆる文人スタイルを貫いたのである。円熟期になってもなお、画名を売ろうと京や大坂へ出ることもなく、生涯紀州で過ごしたのも、隠遁生活、田園生活という文人への憧れであったといえよう。そうした意味では、玉洲は日本における数少ない真の文人といえるかも知れない。


近江の文化財