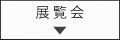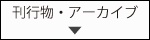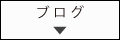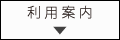4月から5月にかけては、春祭りのシーズン。各地でさまざまな祭りが繰り広げられます。冬の厳しい寒さを耐え忍び、一斉に芽ぶきだす木々や草花、その華やいだ雰囲気そのままに、春のお祭りは人々の心を浮き浮きとさせてくれます。全国のお祭りの中には、一風変わった、いわゆる奇祭と言われるものがいくつかありますが、実は近江にも、少し変わった珍しい祭りがあります。湖北・米原の「鍋冠祭(なべかんむりまつり)」もその1つです。
毎年5月3日に行われる筑摩神社の祭礼は、頭に鍋を被った女性が練り歩くところから「鍋冠祭」と呼ばれています。女性が鍋を被る祭りなど他に見たこともなく、聞いたこともありません。まことにユニークというか、奇祭と呼ばれる所以もそこにあります。この祭り、昨日今日始まったものではありません。悠に千年以上の伝統のある祭りなのです。平安時代中期に成立したとされる「伊勢物語」の中にこの筑摩の祭りが詠われています。「近江なる筑摩の祭とくせなむ つれなき人の鍋のかず見む」とあり、また応徳3年(1086)成立の勅撰和歌集の「後拾遺和歌集」にも登場するなど、平安貴族の間にも広く知られていたことがわかります。いつからこのようなことが行われだしたかはわかりませんが、平安時代にはすでに「氏子の女性が褥を重ねた男性の数だけ鍋を被って神輿に従う」ということになっていました。もし、不正があれば、ただちに神罰が下るとされていました。ですから「伊勢物語」では、「自分に冷たい女性の、鍋の数を見てみたいものだ」と詠っていたのです。
本図に描かれる3人の女性のうち、先頭を歩く婦人は、鍋1つを被り、背筋をのばし毅然とした態度で立つのに対し、後ろの二人は、いずれも鍋2つを被っており、顔を袖で隠すように、恥ずかしげに付き従っています。本当に祭りの雰囲気をよく描いています。
作者の吉村孝敬(よしむら こうけい:1769~1836)は、円山派の画家・吉村蘭州(よしむら らんしゅう)の子として京都に生まれ、字は無辺、蘭陵と号しました。幼少より父から絵を学び、のち応挙に師事して、有力門人の一人に数えられるほどの活躍を見せます。父蘭州は近江・野洲の出身、早くから京都に出、はじめ石田幽汀(いしだ ゆうてい)に師事し、のち応挙門人となります。その一方、西本願寺本如上人に仕え、諸堂の障壁画などの御用を務めました。孝敬も幼少より父について西本願寺に出入りを許され、同寺に多くの作品を遺しました。山水・花鳥画を得意とし、円山派の写実表現をよく伝えています。息子孝文も円山派の画家として、幕末の画壇に重きをなしました。さらにその子孝文も幕末・明治の京都で活躍するなど、代々に渡って円山派の画風を伝え、その普及に努めました。
なお、画中の詩文は、伊勢神宮の神官であり、国学者でもある荒木久守(あらき ひさもり:1779~1853)が、「人しれぬ 我したはへも あらはるる つらき祭に あふみなりけり」と記し、続けて、本居宣長の娘で歌人の美濃(1773~1835)が、「鍋のかず すくなき人に 見るひとの 心は つくまの祭なるらむ」と記しています。
( 上野 良信 )