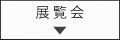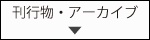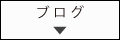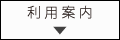平成最後の干支は「亥」でした。今回ご紹介するのは、平成31年(2019)の主役“猪”を描いた作品です。遠景には山が描かれ、樹木の下に横たわるように伏せる雌の猪と、それを見守るように寄り添う雄の猪の姿には、愛情あふれる細やかな観察力がうかがわれます。花や樹枝に動物などを描いて「静動の妙」を表現するのも写生画の手法であり、本図もそうしたものの一つです。
平成最後の干支は「亥」でした。今回ご紹介するのは、平成31年(2019)の主役“猪”を描いた作品です。遠景には山が描かれ、樹木の下に横たわるように伏せる雌の猪と、それを見守るように寄り添う雄の猪の姿には、愛情あふれる細やかな観察力がうかがわれます。花や樹枝に動物などを描いて「静動の妙」を表現するのも写生画の手法であり、本図もそうしたものの一つです。作者の松村呉春(まつむら ごしゅん)は、江戸時代中期から後期にかけて京都画壇を席巻した四条派の始祖です。宝暦2年(1752)に京都の金座役人の家に6人兄弟の長男として生まれ、安永2年(1773)に与謝蕪村の内弟子として入門し、俳諧や南画を学びます。最初は家業を継いで役人生活を続けながら、趣味や余技として学び始めたようですが、安永4年(1775)版の「平安人物誌」の画家の項に名前が載っており、この前後頃から、何らかの事情で金座を辞めて本格的に俳諧師や絵師として身を立てていく決心をしたようです。
天明3年(1783)に蕪村が重病に伏せると、兄弟子である紀楳亭(きばいてい)と共に献身的に看病しますが、同年末に蕪村は亡くなってしまいます。師の死後も、自ら挿図を描いて与謝蕪村遺作句集「新花摘(しんはなつみ)」を出版しました。しかし、この頃から次第に師匠とは対照的な画風である円山応挙に接近していきます。天明7年(1787)頃から、おそらく応挙の紹介で、妙法院門主 信仁法親王(しんじんほうしんのう)のサロンに出入りし始め、法親王側近の絵師となります。同年、応挙を棟梁とする6人の絵師の中に入り、兵庫県にある大乗寺の第一回目の襖絵制作に参加しています。呉春は応挙に弟子入りしようとしたようですが、呉春の画才を認めていた応挙は、師弟関係ではなく友として一緒に、「ただ共に学び、共に励むのみ」と応えたという逸話が残ります。
寛政7年(1795)の応挙没後は、画壇の中心として活躍し、多くの弟子を育てました。京都の四条付近に住んでいたことから、その一門は「四条派」と呼ばれました。晩年の呉春は、病気がちで健康がすぐれず、大作を依頼されても断ったといいます。文化8年(1811)7月、自宅で亡くなります。享年60歳。
与謝蕪村から学んだ文人画の味わいを残しつつ、円山応挙の写実的な画法を取り入れた呉春の画風は、頼山陽(らいさんよう)に「京都の画風は応挙によって一変し、呉春によって再変した」と評されたほどでした。
( 上野 良信 )