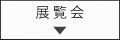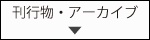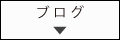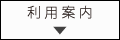紫の打ち掛け、緋色の帯、地模様のある白い着物を身に着けた美女が、白象の背に乗り、静かに文を読む。このような美人画は、江戸時代に入って描かれ出したもので、モデルはほとんどが遊女です。しかし、どの女性も卑しい身分に見えないくらい高貴な雰囲気を醸し出しています。「見立て絵」というものをご存知でしょうか。一見当世風の人物・風俗を描きながら、実は故事や古典文学など、別のものを表現しているという絵です。本図もそうした見立て絵の一つで、「遊女」と「白象」をキーワードにひも解いていくと、有名な「遊女江口君」の物語にたどりつきます。
物語の舞台となった摂津国江口は、淀川と神崎川の分岐点に位置する、平安時代より栄えた港町です。修行僧西行(さいぎょう)が江口の里を通りかかったのは、天王寺詣での帰途でした。突如雨に降られ、この遊里に雨宿りを求めましたが、遊女江口君に断られ、それに抗議する歌を詠んだところ、機知に富んだ見事な返歌でやり込められました。それを機に、すっかり意気投合した二人は、一晩中仏の道の有り難さと、歌をたしなむ面白さなどを語り明かしたといいます。この時の問答歌は『新古今和歌集』に収載されています。
西行と江口君の出逢い。それを元に作られたのが能の謡曲「江口」です。ある旅の僧が江口の里を通りがかります。ここは昔西行が遊女に一夜の宿を乞うて断られた旧跡であることを思い出し、その時西行が詠んだ歌を口ずさんでいると、どこからともなく一人の女が現れ、「何故に西行の歌を口ずさむ」と問いただします。そして遊女が宿を断るときに詠んだ歌を挙げ、「それは西行の身を思ってのことだ」と当時の話をします。いわくありげな様子に、僧が名を尋ねると、自分は遊女江口君の亡霊であると名乗り、迫りくる黄昏の中に消えて行きました。夜更けに僧が、江口君の霊を弔っていると、月夜の川面に屋形船に乗った江口君が現れます。昔の船遊びでの様子を再現し、遊女の境遇を述べ、歌や舞を舞う内に、やがて船は白象になり、江口君は普賢菩薩に身を変えて西の空に消えて行きました。こうした話から、白象に乗る遊女の姿を普賢菩薩に見立てるようになったのです。
作者の駒井源琦(こまい げんき)は延享4年(1747)、京都の根付職人の子として生まれました。円山応挙の最初の弟子で、門弟四天王の一人に数えられます。応挙の作風をよく受け継ぎ、なかでも美人画を得意とし、彩色の美しさ、細部描写の緻密さでは師の応挙を凌ぐとさえいわれます。寛政度御所造営、大乗寺障壁画にも参加するなど、応挙の高弟として広範囲に活躍し、応挙の没後も円山派の発展に務めましたが、寛政9年(1797)、師の後を追うように亡くなりました。
( 上野 良信 )