| 木造阿弥陀如来立像 1躯 | 重要文化財 鎌倉時代 |
| (もくぞうあみだにょらいりゅうぞう) 草津市 観音寺所蔵 | 像高 97.0㎝ |
|
両手で来迎印(らいごういん)を結び、身を乗り出して蓮華の上に立つ、この仏像は草津市芦浦・観音寺の木造阿弥陀如来立像です。切れ長な眼によって作り出された厳しい表情と、柔らかな頬によって表された端正な顔つきが魅力的です。全身にみなぎる気が、今にも風をはらんで動きだしそうな重層的な衣に凝縮されています。高さ90㎝ほどの像ですが、圧倒的な存在感を持っています。 |
※写真をクリックすると、全方面の画像が見られます。 |
| 正面全身 | |
| 斜めから見ると、仏様の立体感がよく分かります。衣のしわも、単なる線じゃなくて、ふくらみを持って作られています。 この仏像は、極楽浄土から往生者の魂を迎えるために、私たちの世界にやってくる姿を表しているため、前に乗り出すような角度で立っています。 |
|
 |
 |
| 左側面全身 | 右側面全身 |
| 仏像は、立体だから見る角度によって違った姿を見ることができます。 阿弥陀如来の名は、「限りない寿命をもつもの」と「限りない光をもつもの」の二つの意味をもつサンスクリット語から名づけられました。現世をあまねく照らす光の仏です。 |
阿弥陀の名前を称(とな)えると、「極楽浄土」という仏様の世界から迎えがきて、その世界に生まれ変わることができると信じられました。 この教えがとても魅力的なので、鎌倉時代以降にとっても篤い信仰が寄せられ、多くの阿弥陀如来像が作られました。 |
 |
 |
| 背面全身 | 頭 部 |
| 後ろの姿は、普通見ることができない部分です。 ちゃんと服のしわや背中の丸み、腰の盛り上がりも表現されています。 |
髪の毛は「螺髪(らはつ)」といって、一本ずつが丸まるようなパーマがかかっています。それに頭の真ん中に「肉髻(
にくけい)」という盛り上がりがあり、これは、仏様の智慧が詰まって膨らんでいます。 仏様は「悟り」という絶対の智慧を持っているから、怒ったり、悲しんだり、にやけたり、大笑いしたりしません。そのことを表すために、眼を半分開いて、口元も穏やかに噤(つぐ)んでいます。 |
 |
 |
| 像 底 | 光 背(こうはい) |
| 足の裏にはいろんなおめでたいものをまとめた「吉祥文(きっしょうもん)」というものが表わされています。 これは、どんな縁起のいいものも、仏様の足下にも及ばないことを表しています。足の裏に吉祥文を描くようになるのも鎌倉時代以降の仏像の特徴です。 |
仏様から光が溢れるように出てくる様子を表現しているのが、後ろの「光背」です。 この仏様では、銅板で想像上の草花を表しています。遠くからみるとよく分からない、草花の表現も丹念に表されています。 |
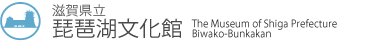

近江の文化財
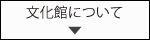
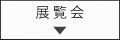
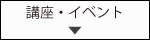
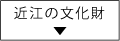
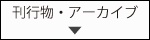
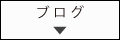
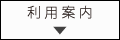

 特に、この阿弥陀如来立像では、伝来の過程で失われてしまうことの多い光背・台座がともに伝来しています。銅製透彫の光背には、華麗な宝相華(ほうそうげ)文様があしらわれ、鎌倉時代の美意識を感じさせます。
特に、この阿弥陀如来立像では、伝来の過程で失われてしまうことの多い光背・台座がともに伝来しています。銅製透彫の光背には、華麗な宝相華(ほうそうげ)文様があしらわれ、鎌倉時代の美意識を感じさせます。