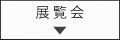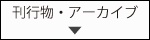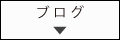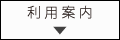全体に細長く、やや湾曲してツルハシのような形状をした、黒っぽい粘板岩質の石。大きさは、長さ19.0cm 、幅5.5cm、 厚さ3.5cm で、中央にはまるで日本刀の鍔のような隆帯が2条めぐり、表面は丁寧に磨き上げられています。 この奇妙な形をした石はいったい何なのでしょうか。
 このような石が土の中から掘り出されたりすると、誰もが驚き、不思議に思ったことでしょう。江戸時代に全国を歩いて奇石を収集した、近江出身の弄石家・木内石亭(1724~1808)も、著書『雲根志』によく似た形の石を載せています。
このような石が土の中から掘り出されたりすると、誰もが驚き、不思議に思ったことでしょう。江戸時代に全国を歩いて奇石を収集した、近江出身の弄石家・木内石亭(1724~1808)も、著書『雲根志』によく似た形の石を載せています。
かつて、このような奇石は「神代石(じんだいせき)」と呼ばれ、神代の時代に使われた石だと考えられていました。江戸時代も中期になって、ようやく人の手によって加工されたものと認識されるようになり、明治時代以降の近代考古学の研究によって、今では、 縄文時代後期から晩期に発達し、一部は弥生時代にも残存する「石器」であることがわかってきました。形状が仏具の独鈷(どっこ)に似ていることから独鈷石とも呼ばれますが、もちろん仏具ではありません。ただ、用途ははっきりしておらず、本来は中央のくびれ部に柄を装着する両頭石斧だったものが、縄文時代晩期にかけて次第に呪術の道具へと変化していったのではないか、と考えられています。
この種の石器は全国で1,200点以上出土していますが、東北地方から関東、中部地方に集中し、近畿地方では比較的珍しいものです。滋賀県では、近江八幡市大中の湖南遺跡、長浜市塚町遺跡など数カ所の遺跡から出土し、東日本縄文社会との交流を示すものとして注目されます。
琵琶湖文化館が所蔵するこの両頭石斧は、天保年間(1830~1844)に坂田郡神照村大字山階(現 長浜市)で井戸を掘っていた時に出土したものです。長く地元で保管されていましたが、昭和のはじめまでに東浅井郡田根村(現 長浜市)出身の郷土史家・田中礎(1872~1960)の手に渡ります。その後、京都大学考古学研究室の島田貞彦(1889~1946)の目に留まり、『滋賀県史蹟調査報告書 第1冊 有史以前の近江』(1928 滋賀県保勝会編纂)の中で紹介されて、広く世に知られることとなりました。この報告書に掲載されたことがきっかけとなったのでしょうか、戦後になり、この石器は滋賀県立産業文化館(文化館の前身)へ寄贈され、その後、文化館が引き継いで現在に至っています。
今から180年も前の江戸時代の出土品ですが、考古学研究の黎明期を経て、こうして現在まで失われることなく受け継がれてきたものです。この石器は、先史時代の人々の生活の一端を物語る資料というだけでなく、滋賀の考古学史を語る上でも欠かせない資料の一つだと言えるでしょう。こういった貴重な資料を、私たちも次の世代へ大切に引き継いでいきたいものです。
※「両頭石斧」は、令和3年(2021)2月6日から3月21日まで、県立安土城考古博物館で開催された、地域連携企画展「琵琶湖文化館の『博物誌』―浮城万華鏡の世界へ、ようこそ!―」に出展されました。